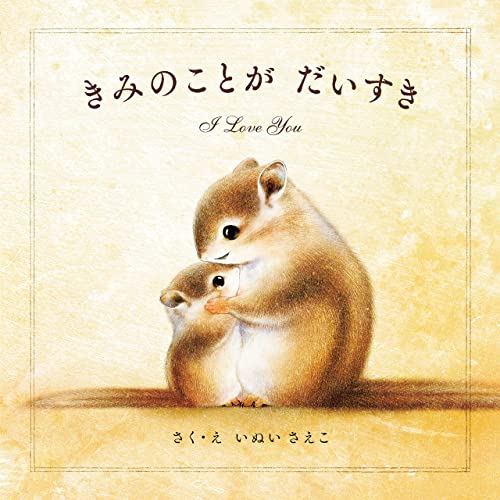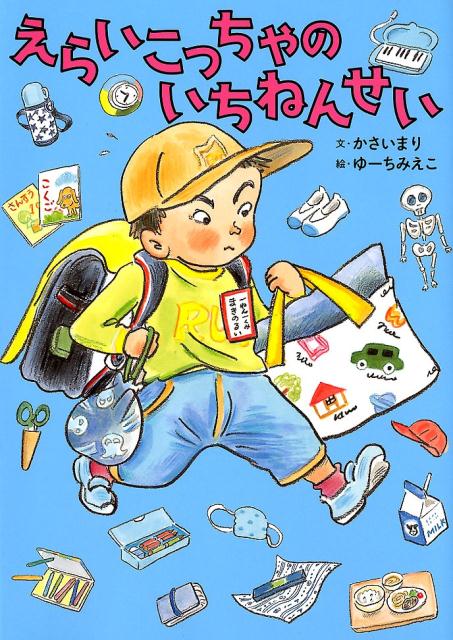【子どもに寄り添う】卒園が寂しい…心のケア方法と子どもにおすすめの絵本13選
卒園は成長の節目としてうれしい出来事ですが、子どもによっては寂しいと感じてしまうことがあるようです。涙を流したり元気がなかったりする様子に、ママはどうしてあげたらいいのか悩んでしまいますね。ここでは、卒園に寂しさを感じている子どもの心のケアの方法と、読んであげたいおすすめの絵本を紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
目次
【体験談】卒園は親も子どもも寂しい
卒園式が近づいてくると、大好きな先生やお友だちと会えなくなることを寂しがる子どもがいます。同時に、我が子の卒園に何とも言えない寂しさを感じてしまうママも多いようです。
毎日手をつないで通った園、ママと離れるのが嫌だと泣いていた子が今では走って教室に入っていく姿、もう着ることはない小さな制服や帽子…。子どもの成長はうれしいはずなのに、自分の腕の中から離れていってしまうようでママは寂しさを感じてしまうのですね。小学校入学に感じる不安も影響しているかもしれません。
とはいえ、寂しいと感じるのは親にとっても子どもにとっても、それだけ園生活が充実していたという証です。「我が子は幸せな時間を過ごせたんだ。ああ良かった」と視点を変えてみると、あたたかい気持ちになれそうですよ。
幼稚園のメンバーがほぼ全員同じ小学校に入学したので、寂しがる様子は息子には見られませんでした。ただ親である私はそうはいかず、小さくてかわいい子ども時代はもう終わりで、あとはどんどん大きくなっていくんだろうなと一抹の寂しさを感じました。
卒園を迎える子どもが「寂しい」と泣いたら?

寂しさを認める
子どもが寂しいと泣いたとき、つい大人は「大丈夫だから泣かないんだよ」と言ってしまいがちです。励ますこと自体は良いことなのですが、まずはいったん寂しいという子どもの気持ちを認め、受け止めてあげましょう。
自分の気持ちをママに伝えられるのは良いことです。親子のあいだに信頼関係が成立している証拠ともいえます。やさしく抱きしめながら「そうだね、寂しいね、ママも一緒だよ」と言ってあげると、気持ちの共有ができて子どもは安心するのではないでしょうか。
楽しい新生活をイメージさせる
新しく始まる生活の楽しい面に目を向けさせるのもおすすめです。1年生になったらできるお勉強や楽しい遠足や、あこがれのランドセルや好きなキャラクターの筆箱を使えることなどを話題にし、ママがうまく誘導して楽しい生活が始まることをイメージさせましょう。
寂しさを否定するのではなく、楽しいことがたくさんあることに気付かせるのがポイントですよ。
卒園する子どもに読んであげたい絵本13選
きみのことが だいすき
発売日:2022年02月
作/絵:いぬいさえこ
出版社:パイインターナショナル
「きみのことがだいすき」は、リスの親子が主人公のやさしさと愛が詰まった絵本です。悲しい気持ちを我慢しなくて良いこと、じょうずにできなくても良いことを心温まる言葉でおくります。
なにがあってもママはあなたが大好き、そんな気持ちが伝わり、入学に向けて不安を感じている子どもの気持ちをやんわりとほぐしてくれることでしょう。
おおきくなるっていうことは
発売日:1999年1月
著者/編集:中川ひろたか,村上康成
出版社:童心社
「おおきくなるっていうことは」は、子どもの新しい門出や節目の時期に贈りたい絵本のひとつです。「大きくなるっていうことは…」というテーマをもとに、着ていた洋服が着られなくなったり歯が生えてきたり、身体的な成長から心の成長まで描かれています。
卒園式ではなぜか泣きたくなったけれどその理由がわからない…と自分自身の心に問いかける子どもたちに、読んであげたい一冊ですよ。
ぐるんぱのようちえん
発売日:2008年04月
著者/編集:西内ミナミ, 堀内誠一
出版社:福音館書店
「ぐるんぱのようちえん」は、ひとりぼっちの大きな像のぐるんぱが、数々の失敗を経て子どもたちが集まる幼稚園をつくり、最後に自分の居場所をみつけるお話です。
楽しかった幼稚園での毎日を振り返りながら「小学校に行っても自分の居場所がみつかるよ」「失敗しても大丈夫」という心強いメッセージを届けられるでしょう。
みんなともだち
発売日:1998年1月
作:中川ひろたか
絵:村上康成
出版社:童心社
「みんなともだち」は、卒園式でよく歌われる「みんなともだち」という歌がそのまま絵本になったものです。歌を知っている子どもに贈るととても喜ばれるでしょう。
学校に行っても、大人になっても、一緒に遊んで大きくなった友だちはずっと友だちだという歌詞は、卒園を前に寂しさを感じている子どもを勇気づけるのではないでしょうか。
えらいこっちゃのいちねんせい
発売日: 2019年01月
著者/編集: かさい まり(著), ゆーち みえこ(絵)
出版社: アリス館
小学校に入学したばかりの主人公の「ぼく」は、学校で困ったことが起こっても、「えらいこっちゃ」とつぶやきながら困難を一生懸命乗り越えていきます。まるで呪文のような「えらいこっちゃ」の不思議な響きと主人公の奮闘ぶりに、「なにかあってもなんとかなる」と思える勇気が湧いてきます。
しょうがっこうへ いこう
「しょうがっこうへいこう」は、「遊んで学べる小学校ハウツー本」としてまとめられました。小学校で勉強することやルールなどを楽しいクイズや迷路などのゲーム形式で学べます。
ユーモアあふれる文章と絵で描かれたページを読み進めるうちに、小学校に進むワクワク感や期待感が高めてくれることでしょう。
しょうがっこうがだいすき
発売日:2011年02月
著者/編集:うい, えがしらみちこ
出版社:学研プラス
著者のういさんは、執筆当時は小学2年生の女の子でした。「しょうがっこうがだいすき」では、小学生の先輩として、新1年生に向けたメッセージを届けます。
子どもの目線で困ったときの対処法や小学校での過ごし方を教えてくれるので小学校生活をイメージしやすく、不安な気持ちをやわらげてくれますよ。
一ねんせいになったら
発売日:2011年3月
著者/編集:まど・みちお, かべやふよう
出版社:ポプラ社
「一ねんせいになったら」は、「友だち100人できるかな」で有名な童謡を絵本にしたものです。歌を聴くと大きな声で歌う園児が思い浮かぶように、絵本に登場する園児たちもみんな元気です。この絵本を読めば「1年生になるって楽しそう」と入学を心待ちにしてくれそうです。
絵本の中には、実際に100人の友だちの絵が描かれたページがあります。どんな友だちがいるのか、一人ひとりをじっくり見るという楽しみ方もおすすめです。
1ねん1くみの1にち
発売日:2010年09月
著者/編集:川島敏生
出版社:アリス館
「1ねん1くみの1にち」とは、小学校に入学するにあたり、1年生の登校から下校までを写真付きで一冊にまとめた絵本です。授業の様子だけではなく、給食の様子や下校後の学校のことまで紹介されているので、小学校での生活がイメージしやすいでしょう。
子どもは、新しいランドセルを背負って登校することにとても緊張するはずです。子どもが入学してから「あ、この授業の風景、絵本で読んだ」などと安心できるように、卒園と同時に読み聞かせるママも多いようですね。
どんなにきみがすきだかあててごらん
発売日:1995年10月
著者/編集:サム・マクブラットニ, アニタ・ジェラーム
出版社:評論社
「どんなにきみがすきだかあててごらん」は、2匹のウサギが相手をどんなに好きか伝え合い、競い合うほほえましいお話です。小さなウサギが身体を精一杯使って気持ちを表現しても、大きなウサギにはかないません。何度も何度も「こんなにも君が好きなんだ」と伝え合うウサギのやり取りを読んでいると、心の中にあたたかい気持ちが生まれます。
卒園を前に子どもの心が不安定になっていたら、この絵本を通して「あなたのことが大好きよ」と伝えてみてはいかがでしょうか。「安心して新しい世界に踏み出していいよ」と伝えてあげましょう。
6さいのきみへ
発売日:2011年3月
作:佐々木正美
絵:佐竹美保
出版社:小学館
「6さいのきみへ」は児童精神科医の佐々木正美氏による絵本です。生まれてから6歳になるまでを振り返り、卒園おめでとう、入学おめでとうと結んでいます。少し小さく生まれたこと、食べ物に頑固で手こずったことなど、描かれたエピソードに我が子を重ねるママもいることでしょう。
この絵本を読んで「私はどうだった」「僕もこういう感じだったの」と赤ちゃんのころを聞きたがる子どももいるようです。生まれてからの話ができる素敵なきっかけとなることで、子ども自身が成長したことを実感でき、1年生になる自分を誇らしく思えるのではないでしょうか。
じぶんでつくる 6さいまでの アルバム
発売日:2000年01月
作/絵:やまわき ゆりこ
出版社:福音館書店
「じぶんでつくる 6さいまでの アルバム」は、生まれた日から6歳までのエピソードを写真を貼ったり絵を描いたりしながらまとめ上げる自分だけのアルバムです。
赤ちゃんのころから今にいたるまでの自分の成長を振り返ることで、自分に自信がつき、自分のことを誇らしく感じられるでしょう。小学校ではどのような自分になるのか、これからの成長が楽しみになる一冊です。
おおきな木
発売日:2010年09月
著者/編集:シェル・シルヴァスタイン, 村上春樹
出版社:あすなろ書房
「おおきな木」は、読み手の年齢やそのときの感情により、さまざまなとらえ方ができる絵本です。卒園を控えた幼稚園児に読み聞かせるには少し早いかもしれませんが、子どもが年齢を重ねたときに読み返して欲しいと、卒園などの節目に贈る親も多いようです。
絵本は、無償の愛がテーマになっているともいいます。さまざまな愛のかたちがあり、与えられる側、受け取る側、そして、受け取ったものを返す側となったとき、どのような愛の形があるのか…と大人も考えさせられる一冊ではないでしょうか。
心のケアに絵本を上手に使ってみよう
卒園することに寂しさを感じている我が子の姿はかわいそうでありながらも、心の成長に気付かされ、うれしく感じる一面もありますね。子どもの気持ちを大切に受け止めて一緒に乗り越えられれば、きっと今後の心の成長を支える大きな経験となるでしょう。紹介した絵本などを上手に使って、心のケアをしてあげてくださいね。
※この記事は2025年1月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。