シングルマザーがもらえる手当・助成は?条件&いくらもらえる?母子家庭の生活の不安を解消
ひとりで子育てと生活と仕事を回していくのは、経済的にも心身面でも負担が大きいですよね。身を粉にして子育てに励むシングルのママやパパを支援するため、各自治体では母子家庭・父子家庭向けの支援を拡充させています。ここでは、児童扶養手当や医療費助成制度などひとり親を対象とする手当・助成について、給付額や受給方法を紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
目次
母子家庭(シングルマザー)の給付金とは?
厚生労働省が行った「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(※1)」によると、母子世帯数はおおよそ 119.5万世帯、父子世帯数は14.9万世帯あります。ひとり親世帯のうち母子家庭は母と子どもで生活している世帯が多いのに対し、父子家庭は祖父母などと同居しているケースが多く、正規雇用の割合も男性のほうが高い割合でした。
収入面にも性別による差があらわれています。母子家庭世帯の平均年間収入は373万円、父子家庭の平均年間収入は606万円となっており、母子家庭の収入は父子家庭より4割ほど低い水準でした。
児童のいる世帯の平均収入は785万円(※2)であることから、特にシングルマザーが厳しい状況におかれていることがわかります。このような背景を受け、ひとり親世帯を支援するためにさまざまな手当・助成制度が設けられています。
児童手当
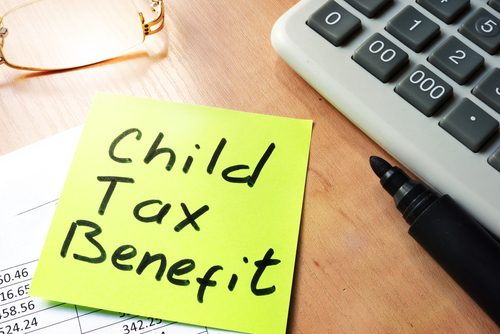
「児童手当」は中学生以下の子どもがいる世帯に支給される手当です。原則として、2歳までは月額1万5,000円、3歳以上は1万円が支給されます。給付を受けるには住んでいる自治体への申請が必要です。認定されると毎年6月・10月・2月に指定の口座へ前月分までの手当が振り込まれます。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
児童扶養手当

「児童扶養手当」は、離婚などによりひとり親となった世帯の児童を養育するために支給される助成金です。原則として18歳になった最初の3月31日までの児童が支給対象となります。
支給額は所得や子どもの人数で異なり、基本額の全額が支給される「全部支給」と部分的な「一部支給」のいずれかが適用されます。児童がひとりで全部支給となったときの給付額は、月額43,070円です。児童扶養手当を受給するには住んでいる自治体への申請が必要で、認定されれば奇数月に指定口座へ手当が振り込まれます。
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成制度は、母子家庭・父子家庭に対して設けられています。ひとり親家庭の親(母もしくは父)や子どもが医療機関などにかかったとき、医療保険の自己負担分から一部負担金相当額が助成されます。住んでいる自治体によって助成内容は異なるため、詳しくは担当の窓口へ問い合わせてみましょう。
こども医療費助成

多くの自治体では、健康保険に加入している中学生以下の子どもを対象に、医療機関などでかかった健康保険診療内の自己負担分を助成する制度を設けています。住んでいる自治体で申請すると、助成を受けるための医療証が交付されます。受給方法や自己負担額は自治体によりさまざまです。詳しい情報は役所の窓口や公式ホームページで確認が必要です。
母子家庭の住宅手当

民間の賃貸住宅を借りているひとり親家庭に対し、家賃を助成する制度を設けている自治体もあります。助成の金額は数千円~1万円前後が多く、所得制限や支給要件、助成額は自治体ごとに異なるため、制度の有無や内容について自治体の窓口で確認してみると良いでしょう。
母子家庭の遺族年金

国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、その人の収入で生活していた「子のある配偶者または子」に対して支給される年金が「遺族基礎年金」です。遺族基礎年金は原則として、子どもが18歳になった最初の3月31日を迎えるまでが支給対象となります。
厚生年金に加入している場合は、遺族厚生年金に遺族基礎年金が加算されます。子どもが18歳になると遺族基礎年金は停止しますが、配偶者が40歳から65歳になるまでのあいだは中高齢寡婦加算が支給されます。
児童育成手当

「児童育成手当」は東京都が設けている制度で、児童扶養手当とは異なるものです。児童育成手当は原則として18歳になった最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭の保護者が受給できます。受給するには申請が必要で、所得や生活状況の審査に通れば、子どもひとりにつき月額13,500円が6月・10月・2月に支給されます。
自立支援教育訓練給付金
「自立支援教育訓練給付金」は、ひとり親の経済的な自立を支援するために設けられた制度で、児童扶養手当の支給を受けているか、それと同等の所得水準のひとり親を対象に、自治体か雇用保険制度が指定した講座を受講した場合に、経費の60%が給付されるというものです。
看護師や介護福祉士などの資格を取得する際の負担を軽減する「高等職業訓練促進給付金等事業」を実施している自治体もあります。詳しくは受講前に自治体で確認しておきましょう。
シングルマザーも受けられる助成や減免制度

母子家庭や父子家庭を支援する制度はほかにもあります。たとえば、精神や身体に障害を持つ児童の福祉を向上するための「特別児童扶養手当」や「 障害児福祉手当」は、対象の児童が20歳になるまで手当が支給される制度です。また、日常生活が困難な場合は「生活保護」を申請できます。生活保護の受給対象になると、生活費、教育費、医療・介護出産など多岐に渡った支援が受けられます。
多くの自治体では児童扶養手当や生活保護などを受給している世帯に対し、交通機関、上下水道料金、放送受信料など生活に必要な料金の割引や減免制度も用意しています。
自治体の母子家庭向け手当て・助成を確認しよう
経済的な支援のほか、将来的に自立した生活が送れるように看護師、介護士、保育士などの資格取得を支援したり、求職活動のノウハウの提供や就労計画の策定を行ったりする自治体もあります。
基本的な手当・助成以外にも、自治体独自の支援制度を設けている場合があるので、心配なことがあれば自治体の窓口で相談してみましょう。申請に必要な書類や受給要件は自治体のウェブサイトなどで確認できます。必要な支援を活用しながら、少しでも子育てと生活の負担を軽くして、未来を明るくしていきたいですね。
※この記事は2023年11月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ままのてチャンネルもおすすめ
YouTubeのままのてチャンネルでは、専門家の先生による育児に関するお役立ち情報やトレンド、オリジナル漫画動画を配信しています。ファイナンシャルプランナーによる、お金にまつわる情報も配信していますよ。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いたします。




