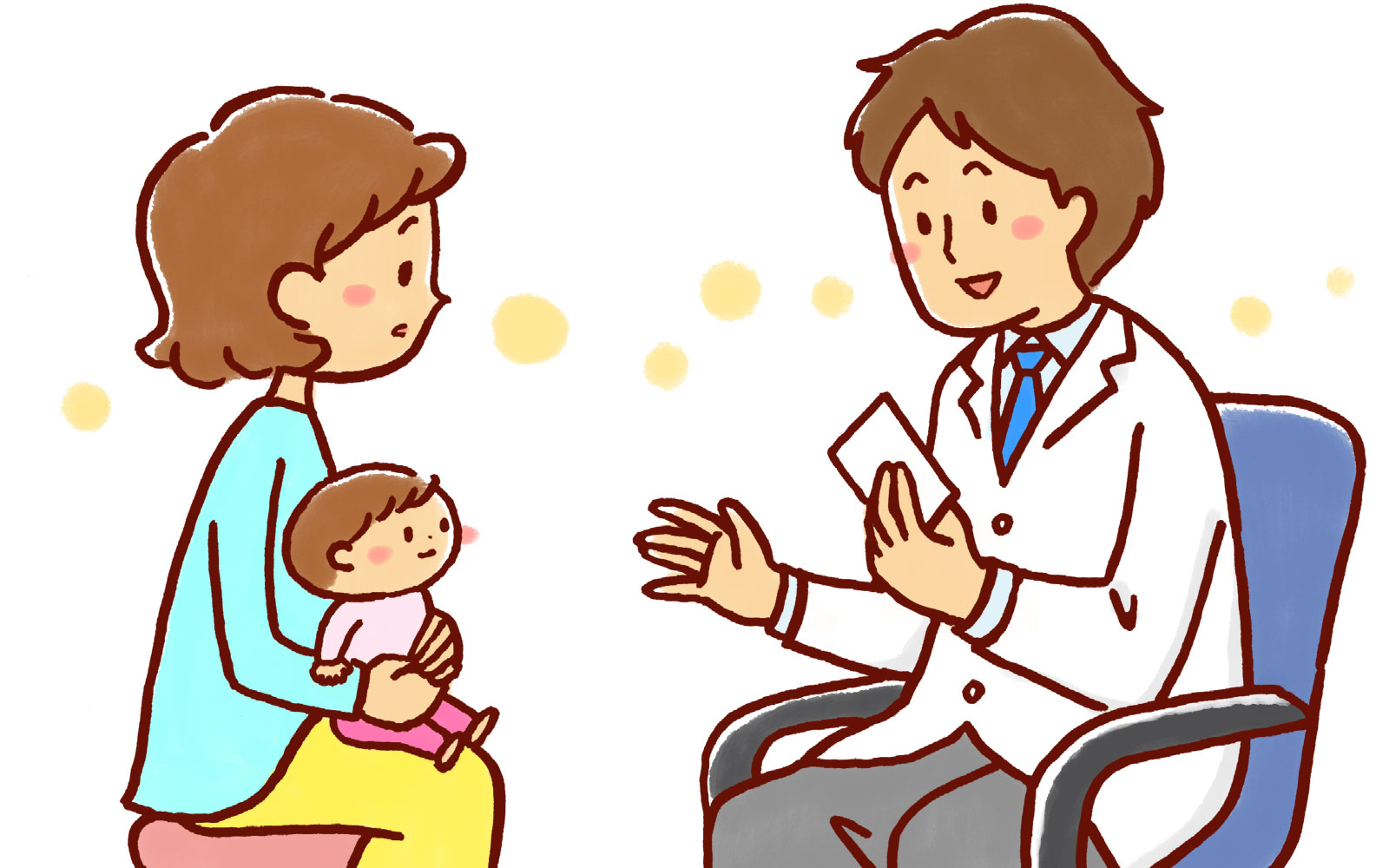【小児科医監修】(2025/2026シーズン)今年のインフルエンザは何型が流行?ピークはいつ?
空気が乾燥し始めるとインフルエンザが流行します。近年、秋や冬だけではなく、春や夏に感染することも少なくありません。ニュースなどで、インフルエンザA型、B型、C型などの名前を耳にしますが、それぞれどのような症状があるのでしょうか。ここでは、インフルエンザの種類とその特徴・流行のピーク・予防方法などについて解説します。
本ページはプロモーションが含まれています
この記事の監修

目次
インフルエンザとは?何型があるの?
インフルエンザウイルスの中で、人間に感染するウイルスは大きく分けて3種類あります。それぞれA型、B型、C型と呼ばれており、ウイルスの型によって症状や経過が異なります。
インフルエンザの一般的な症状として、高熱があげられます。しかし、インフルエンザウイルスの型の違いや個々の体調・体質の影響により、微熱で済む場合も少なくありません。
通常の風邪によく似た症状だからといって放っておくと、重症化してしまうことがあるため注意が必要です。風邪症状を感じたときに正しい判断ができるよう、それぞれのインフルエンザの特徴について知っておきましょう。
インフルエンザA型
インフルエンザA型に感染した際の症状には、次のような特徴があげられます。
・突然の高熱
・寒気、悪寒、関節痛、筋肉痛、頭痛、けん怠感、食欲不振などの全身症状
・鼻水や咳などの呼吸器症状
一般的に最初の3~4日間程度は38℃以上の高熱が続きますが、人によっては1日で急速に下がることもあるようです。高熱が出てから1~3日間は、それに合わせて全身症状が強く表れるでしょう。A型は全身症状が先に現れ、やや遅れて鼻水や咳などの呼吸器症状が強く出る傾向があります。
インフルエンザB型
インフルエンザB型に感染した際の症状には、次のような特徴があげられます。
・熱は高熱が基本だが、微熱症状で済むことがある
・A型に比べると、消化器症状が出ることが多い
インフルエンザB型は、以前は数年単位で定期的に流行していました。しかし、近年は毎年流行している傾向にあります。症状としてはあまり熱が上がらず、微熱程度で済むことも多いでしょう。
A型よりも症状が軽いことから、通常の風邪と勘違いしてしまう場合があります。消化器症状がある場合はインフルエンザの可能性を疑い、自己判断は避けて医療機関を受診しましょう。
インフルエンザC型
インフルエンザC型に感染した際の症状には、次のような特徴があげられます。
・高熱や全身症状が出ることは少ない
・鼻水や咳、のどの痛み
・4歳以下の幼児が感染することが多い
・ほとんどの大人は免疫を持っているため、感染しにくい
インフルエンザC型は、幼児が感染することが多いウイルスです。一般的に4歳以下の子どもが感染するケースが多く、乳児や幼児がいる場合はC型の症状も把握しておくと安心です。
風邪に似た症状で終わる場合が一般的ですが、まれに重症化することがあります。重症化した場合には、高熱・嘔吐・下痢・腹痛・発疹などの症状が現れるため、症状が軽いうちから注意深く様態を観察しましょう。
インフルエンザC型のウイルスは、一度免疫が付くと長期間持続するといわれています。再び感染したとしても軽症で済むケースが多く、通常の風邪と認識してしまうことも珍しくないようです。
各インフルエンザの特徴を知っておくと、気だるさを感じたり発熱したりした際にチェックしやすいでしょう。医療機関を受信する際、医師へ適切に状況を伝えるためにも、慌てずに症状を確認してください。
インフルエンザが流行する時期はいつ?

インフルエンザは、空気が乾燥する時期になると流行する傾向にあります。これは、気温や湿度が低くなるとくしゃみや咳による飛沫(ひまつ)が空気を通して蔓延しやすくなるためです。気温が低い時期はより室内で過ごすことが増え、閉ざされた空間にいることで感染者が増えるとされています。
インフルエンザが流行する期間は、ウイルスの型によって異なります。それぞれの型が流行しやすい時期は次の通りです。
・インフルエンザA型:12~2月
・インフルエンザB型:2~3月
・インフルエンザC型:ピークは1~6月とされていますが、どの時期でも感染する可能性があることから通年性インフルエンザとも呼ばれています。
【2025/26シーズン】今年のインフルエンザの流行状況は?

厚生労働省が全国に3,000ある定点医療機関(※1)からの報告をまとめたデータによると、2025/2026シーズンが開始した2025年第36週(9月1日~9月7日)のインフルエンザ患者報告数は1,949人でした。第40週(9月29日~10月5日)の報告数は6,013人に増えています。
2025/26シーズンはまだ始まったばかりですが、第39週(9月22日~9月28日)の感染症発生動向調査で、1インフルエンザの定点当たり報告数が1.04を上回り、流行シーズンに入ったと発表されています。
2024/25シーズンは第44週で流行期に入り、第52週に報告数が64.39でピークに達しています(※2)。この数値は、1999年に感染症法にもとづく現行の報告体制となって以降最大の数値でした。
今年は例年よりも早い段階で流行期に突入しています。10月には2025年度のワクチン接種が始まっています。早めのワクチン接種と、マスクの着用や手洗いなど基本の感染対策をとるようにしましょう。
※2025年10月時点の情報です。詳しくは参考文献をご参照ください。
今年のインフルエンザの流行は何型?A型が流行?

国立健康危機管理研究機構の感染症情報提供サイト掲載された「週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数」を見ると、2025/26シーズンがはじまった36週から40週のあいだではAH3亜型(A香港型)が多い傾向にあります(※3)。昨シーズンはAH1pdm09がもっとも多く報告されていました。
2025/26シーズンは39週に定点あたり報告数が1.04となり、流行シーズン入りが発表されています。今後、複数の型が流行すると、それぞれに感染する可能性があり、A型に2回、A型・B型それぞれ1回ずつ感染するといったケースも見られます。
何型のインフルエンザウイルスが流行するかは、地域によってばらつきがあります。子どもが通っている保育園や幼稚園、小学校などでの流行状況によっても異なります。各都道府県の公式ホームページや感染症情報センター、地域の小児科の情報を確認すると周りで流行している型が把握しやすいので、情報に耳を傾けておくと良いでしょう。
※2025年10月時点の情報です。詳しくは参考文献をご参照ください。
インフルエンザの予防方法

1.予防接種
インフルエンザを予防するためには、予防接種が効果的といわれています。インフルエンザにかかった場合、重症化を防ぐ効果が期待できます。
2.手洗い、うがい、洗顔
インフルエンザに感染している人が触った物には、ウイルスが付着している可能性があります。インフルエンザウイルスが付着した手で目や鼻・口に触れると、ウイルスに感染する可能性が高まりまるため、清潔を保つことが大切です。
ウイルスの感染を防ぐためにも、こまめに手洗い・うがいをして手や指に付いたウイルスを取り除きましょう。手洗いと同時に顔を洗うと、予防の効果が高いとされています。
インフルエンザだけでなく風邪を予防するためにも、日ごろから手洗い・うがいの習慣を付けておくと良いでしょう。
3.マスクを着用する
咳やくしゃみからの飛沫(ひまつ)中のウイルスは、インフルエンザの主な感染経路とされています。マスクをして飛沫を浴びないように気を配ることが、インフルエンザ感染の予防につながります。
自分や子どもが咳やくしゃみが出ているときにも、マナーとしてマスクを着用し、周囲に感染しないよう配慮できると良いですね。
4.ウイルス感染者と物を共有しない
インフルエンザにかかっている人が使った物には、ウイルスが付着している可能性があります。家族がインフルエンザにかかっている可能性がある場合、タオルやコップを共用しないよう気を付けましょう。
5.適度な湿度の保持と換気
インフルエンザウイルスは空気が乾燥していると活発に活動するといわれています。室内が乾燥しやすい季節は、加湿器などを使用して湿度を50~60%に保つと良いでしょう。
ウイルスを室内に蔓延させないためにも、定期的に換気するのも効果があります。
6.休養と栄養バランスの取れた食事
疲れているときや体調が悪いときは、インフルエンザに感染しやすくなります。日ごろからしっかりと睡眠や休息を取り、栄養バランスを考えた食事を摂ることが、インフルエンザの予防につながります。
7.人混みは避ける
人混みや繁華街に出かけて多くの人と接すると、インフルエンザに感染する可能性が高まります。妊娠中の方や小さな子どもは、インフルエンザが流行している時期はなるべく人混みや繁華街を避けるよう心がけると安心です。
やむを得ず人混みに出るときはマスクを着用し、帰宅後はすぐに手洗い・うがいをすることをおすすめします。
インフルエンザの流行に備えるためにしっかりと予防しよう
インフルエンザは、気温が低く乾燥しやすい寒い季節に流行る傾向があります。インフルエンザウイルスに感染すると、高熱が続いたり消化器官に症状が出たりするケースがほとんどです。インフルエンザが疑わしい場合、自己判断は避けて医療機関を受診するようにしましょう。
いざインフルエンザにかかった際に慌てないためにも、インフルエンザの症状や流行している型を知っておくと安心です。年々、インフルエンザが猛威を振るっている地域も少なくありません。インフルエンザに感染しないためにも、予防接種を受けたり手洗い・うがいを徹底したりと予防を心がけましょう。
※この記事は205年10月時点の情報をもとに作成しています。
お役立ち情報「ままのてチャンネル」もおすすめ
ままのてチャンネルでは、医療や生活のお役立ち情報、癒やしを届ける漫画動画も随時配信しています。ぜひチャンネル登録してくださいね。