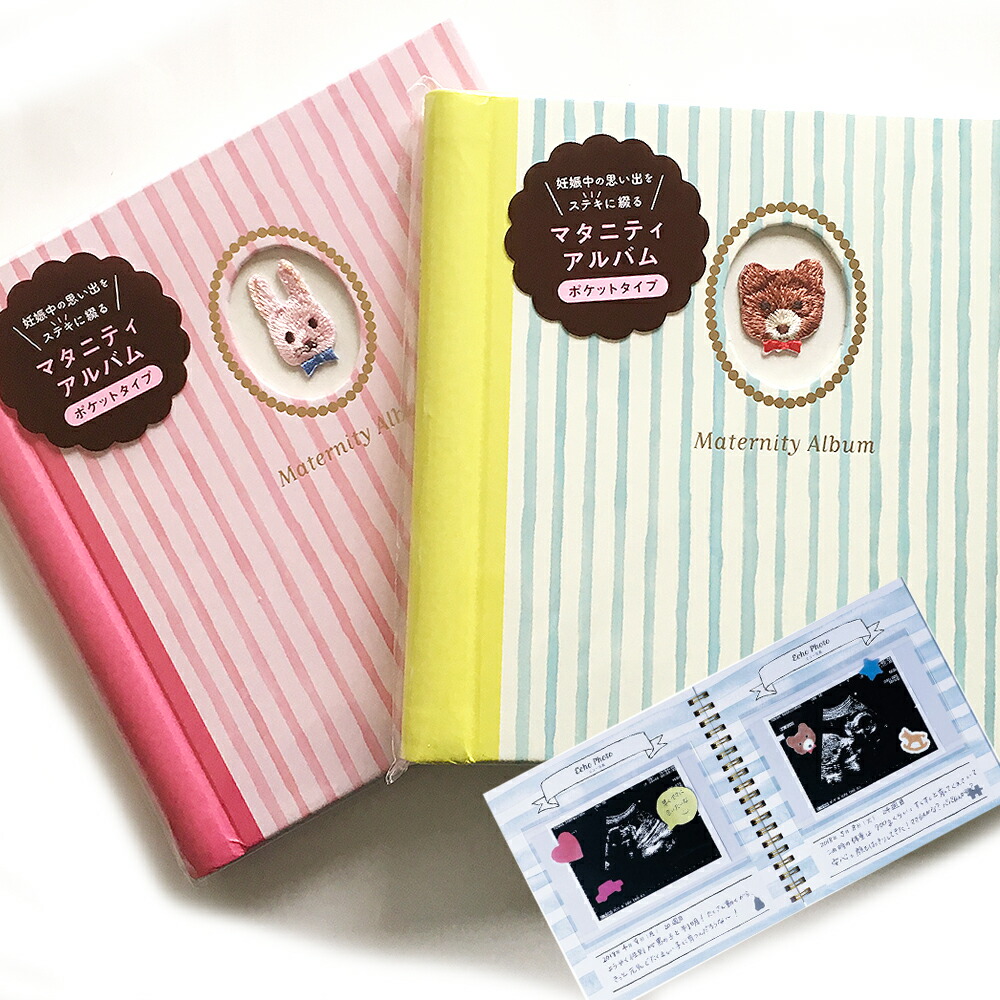【新プロジェクト始動】「共育(トモイク)プロジェクト」とは?育児の“ワンオペ”をなくすために、社会が動く
「ワンオペ育児」や「とるだけ育休」からの脱却を目指し、2025年7月に厚生労働省は「共育(トモイク)プロジェクト」をスタートさせました。これまでの「イクメンプロジェクト」をリニューアルし、社会全体を巻き込んだ「共育て」を後押しする取り組みです。新プロジェクトで何が変わるのか、概要やポイント、今後の取り組みを紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
目次
「共育(トモイク)プロジェクト」ってどんな取り組み?
ワンオペ育児の解消を目指す新しいプロジェクト
2025年7月4日、厚生労働省から「共育(トモイク)プロジェクト」の開始が発表されました。これまで10年以上続いてきた「イクメンプロジェクト」の後継となるもので、共働き・共育てを推進する厚生労働省の広報事業として、家庭や職場における「ワンオペ育児」の解消、そして「共に育てる社会」の実現を目指し、普及・啓発に取り組みます。
「共育(トモイク)プロジェクト」が取り組む課題
これまでの「イクメンプロジェクト」は、男性が積極的に育児に関わることや、育休を取りやすくするための社会的な機運づくりを目的としてきました。その成果もあり、2023年度(令和5年度)の男性の育休取得率は30.1%と過去最高を記録しています。
しかし、育児や家事の実態に目を向けると、ママたちにとって満足な状態とはいいがたい現状があります。たとえば、パパが育休を取得しても「短期間」で終わってしまうケースが多いこと、家事や育児の実質的な負担は依然としてママに偏っていることなどが課題として残されています。
長時間労働や職務の集中など、パパが育児に関わりづらい職場環境も問題です。こうした実状を受けて、「共育(トモイク)プロジェクト」は単なる「育休取得の推進」にとどまらず、家事・育児の「実質的な分担」や、「職場の働き方改革」にも踏み込むかたちでリニューアルされました。
「共育(トモイク)プロジェクト」が生まれた背景は?

2023年にこども家庭庁が打ち出したこども・子育て政策「こども未来戦略」の中で、今後3年間で子育て支援施策を具体的に実施していくための政策として「加速化プラン」がまとめられました。
この加速化プランには4つの政策が盛り込まれ、そのうちのひとつとして「共働き・共育てを応援」が打ち出されています。
| 1.若者・子育て世帯の家計を応援 |
| 2.すべてのこどもと子育てを応援 |
| 3.共働き・共育てを応援 |
| 4.こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 |
2025年4月からは、これらの政策を実現するために「こども・子育て支援」の充実が図られました。共働き・共育てに関しても、育児休業給付率の引き上げや看護休暇の見直し、パパ育休をとりやすくするための取り組みなど、さまざまな推進策が設けられています。
このような企画の立案や総合的な調整は、こども家庭庁を中心として文部科学省や厚生労働省など各省庁が連携して行っています。しかし、体制を強化し、制度や施策を拡充させるだけでは、ママの「ワンオペ育児」やパパの「とるだけ育休」はなくなりません。確実な実行につなげるには、組織や社会にはたらきかけ、現代の子育てに通じた意識のアップデートが必要なのです。
「共に育てる」が当たり前になる社会へ

女性の家事関連時間は男性の約3.9倍
パパの育休取得率が上がった今でも、育児は「ママがひとりで抱えるもの」とされがちです。共働き家庭でさえ、「家事育児のほとんどをママが担当している」「夫婦間で“見えない負担”に差がある」といった「ワンオペ」を嘆く声が多く聞かれます。
実際、総務省が行った「2021年社会生活基本調査(※1)」で、6歳未満の子どもを持つ夫婦の家事、介護・看護、育児、買い物にかけた1日の合計時間を示した「家事関連時間」にも、ママの負担が大きい傾向があらわれています。
※表は総務省「2021年社会生活基本調査」 6歳未満の子供を持つ夫・妻の家事関連時間の推移をもとに作成
■パパの家事関連時間の推移(時間.分)
2011年 | 2016年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 家事関連時間 (合計) | 1.07 | 1.23 | 1.54 |
| 家事 | 0.12 | 0.17 | 0.30 |
| 介護・看護 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 育児 | 0.39 | 0.49 | 1.05 |
| 買い物 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
■ままの家事関連時間の推移(時間.分)
2011年 | 2016年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 家事関連時間 (合計) | 7.41 | 7.34 | 7.28 |
| 家事 | 3.35 | 3.07 | 2.58 |
| 介護・看護 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 育児 | 3.22 | 3.45 | 3.54 |
| 買い物 | 0.41 | 0.36 | 0.33 |
2021年の調査結果は、パパの家事関連時間が1時間54分なのに対してママは 7時間28分でした。近年、男性の家事関連時間は増加傾向、女性の家事関連時間は減少傾向にあるものの、いまだ男女で5時間34分の差があります。
職場も、家庭も、脱・ワンオペ
「共育プロジェクト」の「共育(トモイク)」とは、「共に育てる」という意味を込めた言葉です。ここでの「共に」が指す相手は、パパとママのふたりだけではありません。「一緒に働く人」そして「職場」と共に、「社会」と共に、という意味も含まれます。
これを実現するために、「共育プロジェクト」では、企業へのはたらきかけを積極的に行っていきます。キーワードは「職場も、家庭も、脱・ワンオペ」。ママの「ワンオペ育児」やパパの「とるだけ育休」から脱却し、誰もが「自分らしい働き方」と「育児への関わり」を両立できる社会を目指します。
注目ポイント①:企業へのアプローチを強化!

「共育プロジェクト」では、育児と仕事の両立を個人の努力だけに任せるのではなく、企業も主体となって取り組むことを重視しています。これは「仕事と子育ての両立」が、女性だけでなく男性や職場全体に関わる課題であるという考えに基づくものです。
そのため企業に対するアプローチを強化し、「共育」の実行を後押ししていきます。それと同時に、「共育」の推進が企業にとってどのような効果をもたらすのか伝えていくことも「共育プロジェクト」の大切な役割です。
「共育」を推進することは、若い世代の離職率の低下や、企業の生産性向上といった効果を生むと考えられます。女性の活躍の場が広がり、女性リーダーの育成にもつながるでしょう。そうした未来を見据え、企業と共に、「共育」を推進していきます。
今後の活動例
企業の取り組みを促すために、「共育プロジェクト」では以下のような活動が予定されています。
子育てをしている当事者はひとりではありません。介護中であったり闘病中であったりと、サポートが必要な人はほかにもいます。多様な人が働く職場で「共に育てる」「共に助け合う」ための雇用環境や組織のあり方などについて、管理職・社員向けに研修動画などを作成・配信し普及啓発を行う予定です。企業表彰、家事・育児タスクの可視化なども検討されています。
自治体の「両親学級」では、妊婦体験、沐浴やおむつ替え、抱っこの仕方、離乳食の進め方などを学ぶのが一般的ですが、企業版の「両親学級」は、男性の育児参画を増やすことを目的に開催します。具体的には妊娠中・出産・育児の基礎知識、女性の社会進出と働き方、育休中の家事・育児の分担や働き方の見直しについて学べる場を提供します。
高校生・大学生・入社5年目までの若手社員を対象に意識調査を実施し、その結果をもとに企業研修や支援ツールを構築していきます。タスクシェアの推進なども行う予定です。
注目ポイント②:「家庭の中の分担」まで踏み込む

このプロジェクトのもうひとつの特徴は、「家庭の中」にもアプローチしている点です。
「パパが育休を取ったけど、実際は家事・育児は全部ママ任せだった」「言われたことしかやらない・面倒くさいことはママ任せ」「夫が体調を崩していつものルーチンから数日離れたら、そのまま家事・育児からフェイドアウト」など、あちらこちらで夫婦の問題が噴出しています。
そんな実態を変えていくために、「夫婦で育てる」ためのきっかけ作りにも力を入れていくそうです。
今後の活動例
夫婦で育てることが当たり前になるように、「共育プロジェクト」では以下のような活動を予定しています。
パパの育児休業を「とるだけ育休」とさせないために、家庭内のタスクを見える化し、男女の家事・育児分担の見直しをすすめるきっかけを提示します。
男性の意識をアップデートするとともに、女性も自身の母親像・働き方について見直す必要があります。「共育プロジェクト」では夫婦の「話し合い」を促し、夫婦で共に育てる環境づくりをすすめます。
「共育プロジェクト」公式サイト内に、ユーザー投稿型コンテンツを作成し、職場・家庭内においてそれぞれが実践している「共育」のヒントを発信していきます。
ロゴに込められた想い
プロジェクトのロゴには、「違う色=多様な立場の人たち」が協力し合うことで、初めて「育児はひとりで抱えるものではなくなる」という意味が込められています。
家庭・職場・社会がひとつのパズルを完成させるように、それぞれの役割を担っていくこと。それが「共育」の本質であると伝えています。
どんな人がプロジェクトに関わっているの?
「共育プロジェクト」には、子育てや働き方改革に関わる11名の有識者が委員として参加しています。多様な視点を持つメンバーが関わることで、現場感覚に寄り添ったプロジェクトが進められそうです。
| 羽生 祥子(座長) | ・著作家/メディアプロデューサー ・株式会社羽生プロ 代表取締役社長 |
| 大久保 髙明 | ・有限会社フタバスポーツ 代表取締役 ・協同組合日専連旭川 副理事長 |
| 大畑 愼護 | ・株式会社ワーク・ライフバランス 働き方改革コンサルタント/経営企画室室長 |
| 上条 厚子 | ・NPO法人ママライフバランス代表理事 ・名古屋市男女平等参画審議会委員 |
| 佐藤 竜也 | 株式会社カラダノート 代表取締役 |
| 多賀 太 | 関西大学文学部 教授 |
| 田中 茜 | 東北文化学園大学 助教 |
| 林田 香織 | ・NPO法人ファザーリング・ジャパン 理事 ・wonderLife LLP 代表 |
| 平野 翔大 | Daddy Support協会 代表理事 |
| 広中 秀俊 | 育Qドットコム株式会社 代表取締役社長 |
| 渡邉 将基 | 新R25編集長 |
「共育(トモイク)」は、わたしたちの未来

共育プロジェクトは、決して「父親だけのもの」ではありません。 そして、「働いている人だけの話」でもありません。ママもパパも、職場も社会も、みんなが子育てを支え合える……。そんな社会を目指す大きな一歩が、今まさに踏み出されました。
「パパがもっと家事育児に関わってくれたら…」
「もっと家庭内の役割を“見える化”したい」
「社会がもっと柔軟に働き方を受け止めてくれたら…」
そう願うすべてのママ・パパにとって、このプロジェクトは希望の光になるかもしれません。
ままのてでも、今後この「共育」の考え方を応援し、みなさんが家族らしい形で「共に育てる」ためのヒントを発信していきます。
「共育(トモイク)プロジェクト」の今後に期待
現在、「共育プロジェクト」のティザーサイトが公開されていますが、8月下旬~9月頃には、本サイトの公開が予定されています。興味がある方はぜひ、厚生労働省の公式サイトや今後の発信にも注目してみてください。
ひとりで頑張りすぎなくても良い。そう思うだけで、心がすっと軽くなり、視野が広がるかもしれません。「育児はみんなでするもの」というあたたかい輪が、社会全体に広がっていきますように。
わたしたちも、共に育てる未来を応援していきます。
※この記事は2025年7月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。