【生後何日?生後何ヶ月?】赤ちゃんの月齢の数え方!わかりにくい数え方・計算方法を簡単解説
赤ちゃんの月齢の数え方はわかりにくく、勘違いをしてしまっているママも少なくありません。特に赤ちゃんの行事がある場合、生後何日目か迷うこともあります。ここでは赤ちゃんの月齢の数え方を紹介します。生後の数え方には2種類あり、数え方の使いわけや赤ちゃんが生まれてすぐにある行事、出生届の提出期限なども参考にしてみてくださいね。
本ページはプロモーションが含まれています
目次
赤ちゃんの月齢の数え方
乳幼児健康診査や定期予防接種、各種の申請手続きに赤ちゃんが生後何ヶ月か計算する場面は意外と多いものです。しかし、赤ちゃんの生後の数え方を誤って認識している人は少なくありません。
赤ちゃんの行事などプライベートなことであればある程度融通がききますが、正しい数え方を知らないと、自治体の助成が受けられなかったり、各種の申請が滞ったりと不利益が生じてしまうことがあります。公的な場面で生後何ヶ月か計算する方法や、赤ちゃんの行事で使える生後の数え方を見ていきましょう。
年齢計算に関する法律
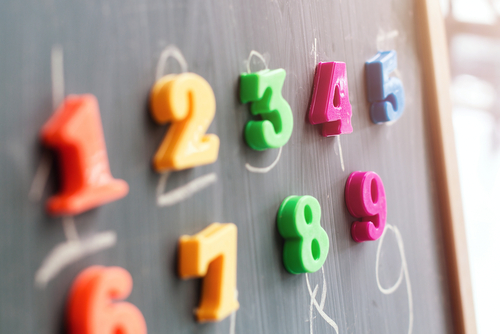
年齢の計算は、1902年(明治35年)に制定された「明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)」と民法第143条で定められています。この法律で、誕生日の前日が終わるときに年齢が加算されると規定しています。
少しわかりづらい解釈ですが、生まれたばかりの赤ちゃんは翌年の誕生日を迎える前日の24時0分にひとつ年をとり1歳になるという考え方を示しています。
日々の生活の中では、24時0分は次の日付の午前0時ととらえるのが一般的かもしれません。しかし、年齢を計算するときの法律上の解釈では、午後12時と午前0時はまったく別物で、年をとる瞬間が属しているのは誕生日前日の午後12時と考えます。
4月1日生まれの子どもが前年度の学年になるのはこの規定によるものです。定期予防接種の対象者の解釈にもこの規定が適用されているため、生後何ヶ月か計算する際は生まれた日と同じ日付を迎える前日に月齢を加算します。
赤ちゃんの月齢の数え方は2種類ある

一般的な数え方
月齢の数え方は、年齢計算に関する法律により赤ちゃんが生まれた日を生後0日としています。この生後の数え方を踏まえ、赤ちゃんが生まれた週は生後0週、生まれた月は生後0ヶ月、生まれた年は0歳と数えます。
赤ちゃんの月齢は、月齢を知りたい日(対象日)がある月の生まれた日と同じ日付の前日に変わります。ひと月の日数が30日や31日であっても生後の数え方には影響しません。4週間経過したら、あるいは30日経過したらと、日数や週数によって月齢が変わるわけではないのです。
日本古来の数え方
現在では、赤ちゃんが生まれた日を生後0日と数えますが、元々日本では赤ちゃんが生まれた日を生後1日と数えていました。古来日本では、年齢を数え年で数えていたため、生後の数え方もそれにならっていたのです。現在でもお七夜などの伝統的な行事では、この日本古来の数え方が用いられます。ただし、地域によって異なるケースもあります。
生後何ヶ月か計算する方法

生後何ヶ月かを計算するときは、今現在の月から誕生月を引いて月齢を導きます。今現在の月の数字が誕生日よりも小さい場合は、その月に12を足してから誕生月を引いて生後何ヶ月かを計算します。4月生まれの場合、12月は「12-4」で生後8ヶ月、1月は「(12+4)-6」で生後10ヶ月です。
ただし、月齢はその月の生まれた日と同じ日付を迎える前日に変わるため、月が替わったからといって月齢が増えるわけではないので注意しましょう。
赤ちゃんの行事は日本古来の数え方で数える

お七夜やお食い初めなど、赤ちゃんの行事にはさまざまなものがあります。これらの行事は日本古来の数え方が用いられ、生まれた日を生後1日とする数え方をします。
お七夜は生後7日目
お七夜(しちや)とは、生後7日目の夜に行うお祝いです。赤ちゃんの命名式をしてからお祝い膳を囲むのが正式なお祝い方法ですが、現代ではママと赤ちゃんの退院と重なってしまうこともあり、お七夜を行わない家庭も少なくありません。命名式で使う命名書はベビー用品店などで販売されているので、探してみてくださいね。
お宮参りは生後30日前後
お宮参りは、神様に赤ちゃんを初めてお披露目する儀式です。男の子は生後31日や32日、女の子は生後32日や33日に行うことが多いです。ただし、お宮参りの時期は地域によってさまざまで、生後3ヶ月頃に行うところもあります。
また、お参りをしてお賽銭をする方法もありますが、お祓いと祝詞をお願いするときは初穂料が必要で、5,000~1万円が目安です。神社によっては一律で金額が決まっていることがあるので、事前に確認しておきましょう。
お食い初めは生後100日~120日ごろ
お食い初めは、生後100~120日頃に行います。「生涯で食べることに困らないように」との願いを込めて、食事を食べさせるふりをします。献立の基本は、一汁三菜です。メニューは地域によって異なりますが、一般的なものは以下になります。
・尾頭付きの鯛
・赤飯
・お吸い物
・香の物
・歯固めの石
お食い初めに必要なものがすべてそろった「お食い初めセット」も販売されているので、準備に時間がとれそうにないママは、そちらを利用しても良いですね。
出生届の提出期限に注意しよう

出生届は日本古来の数え方
赤ちゃんの予防接種などは、赤ちゃんが生まれた日を0日とする一般的な数え方をしますが、出生届は日本古来の数え方をするため注意が必要です。出生届の提出期間は、赤ちゃんが生まれた日を含めて「14日以内」となります。
つまり、4月1日生まれの赤ちゃんの場合、4月15日ではなく、14日までに提出するようにしましょう。ただし、提出期限が土日、祝日の場合は次の開庁日まで期限が延長されることがあるため、最寄りの役所に尋ねてみましょう。
提出期限を過ぎたらどうなる?
出生届の提出期限を過ぎてしまったからといって、提出そのものができなくなるわけではありません。しかし、正当な理由がなく提出が遅れた場合、5万円以下の過料が課せられることがあるため、期限はしっかり守るようにしましょう。
海外で出産したときの出生届の提出期間は、赤ちゃんが生まれて3ヶ月以内です。赤ちゃんが生まれた国で国籍を取得していると、期限を過ぎたら日本国籍を失うことになります。出生届を提出すること自体できなくなるので気を付けましょう。
定期予防接種における年齢の解釈

赤ちゃんが受けられる予防接種のうち、自治体が行う定期予防接種の費用は公費で賄われます。決められた期間内に接種すれば、自己負担はないか一部の負担で済みます。定期予防接種の対象となる年齢を1日でも過ぎると定期接種としては認められないため接種対象の年齢は正確に把握しておきましょう。
定期予防接種の対象となる年齢の解釈については、厚生労働省が以下のようにまとめています。
| ◯歳に達したとき | 翌年の誕生日の前日の午後24時に1歳年をとる 例:4月1日生まれの人は3月31日の午後24時に1歳に達した |
| ◯歳に達するまで、至るまで、至った日まで | 誕生日前日まで(誕生日前日は含む、誕生日当日は含まない) 例:4月1日生まれの人の「1歳に達するまで」は、3月31日まで |
| ◯歳以上 | 誕生日前日を含む日付から数えはじめる 例:4月1日生まれの人に「1歳以上から接種可能」とした場合は「3月31日から接種可能」という意味になる |
| ◯歳未満 | 誕生日前日まで 例:4月1日生まれの人に「1歳未満まで接種可能」とした場合は「3月31日まで接種可能」という意味になる |
| 生後◯ヶ月に至るまで | 対象となる月の生まれた日と同じ日付の前日まで 例:4月1日生まれの人は翌月の生まれた日と同じ日付(5月1日)の前日(4月30日)に生後1月を迎える |
| 対象の月に同日となる日が存在しない場合 | 対象となる月の最後の日で考える 例:1月31日生まれの人は、2月28日(閏年は29日)に生後1ヶ月を迎える |
| 生後◯ヶ月から生後●ヶ月に至るまでのあいだ | ○ヶ月後の生まれた日と同じ日付の前日から●月後の生まれた日と同日の前日まで 例:4月1日生まれの人の生後3ヶ月から6ヶ月は6月30日から9月30日までの期間内を指す |
| 出生○週○日後から | 生まれた日は0週0日、生まれた日の翌日から出生0週1日後として数える 例:4月1日生まれの人の出生1週後からは4月8日からとなり4月8日は含まれる |
各都道府県では、この解釈をもとに対象者を定めています。2014年度以前は「年齢は誕生日の前々日の24時に加算する」と解釈されていましたが、現在は「誕生日の前日の24時に加算する」と周知されています。
なお、「○歳以上」とするとき、厳密にいうと前日の23時59分まではその年齢に達していませんが、午後24時に予防接種することは一般的ではないため、日中に接種を受けられるように配慮されています。「○歳未満」とするときは、厳密に午後24時に年齢に達すると考え、前日の午後24時までは接種可能です。
■表は「定期の予防接種における対象者の解釈について(事務連絡)」を加工して制作
「新生児」「乳児」はいつまで?

月齢の数え方だけでなく、「新生児」や「乳児」の定義を知らないママも少なくないのではないでしょうか。母子保健法によると、新生児は「出生後28日を経過しない乳児」、乳児は「1歳に満たないもの」とされています。
ちなみに「児童福祉法」では、「幼児」は「満1歳から小学校就学の始期に達するまで」と定義されており、それ以降から18歳までは「少年」と呼ばれます。
月齢の数え方に関する体験談

月齢の数え方について、娘を出産するまではあまり考えたことがありませんでした。出生届の提出期間について、何の疑いもなく、生まれた日を0日と数えるものだと思っていたため、記入例を読んでいるときに誤りに気付きとても驚きました。
幸い期限に余裕をもって提出する予定だったので問題はなかったのですが、期限を過ぎてから勘違いに気づいていたらと思うと反省してなりません。
とあるアプリでお食い初めの日程を確認して、お店にお祝い膳を予約しました。ところがよく考えると、その日にちは生後99日目です。予約の日程を間違えたと慌てましたが、生後月齢の数え方は2パターンあることを知りました。お食い初めは日本古来の数え方をするため、生まれた日を生後0日とする一般的な数え方とずれが生じることを知り、安心しました。
2種類の月齢の数え方を使いわけよう

2種類の月齢の数え方に混乱してしまう人もいるかもしれませんが、基本的に、日本古来の行事以外は一般的な数え方をすると認識しておきましょう。ただし、出生届のように例外がある場合もあるので、前もって確認しておくことを怠らないようにしてくださいね。
年齢に関する解釈も正しく理解することが大切です。疑問に思うことがあれば、自治体の窓口で確認しておくと安心です。
「ままのて」が妊娠・育児中のママをサポート
ままのてが提供する、妊娠・育児中の疑問や不安・悩みをサポートするアプリ「ままのて」。妊娠週数や赤ちゃんの月齢にあわせて、ママへのメッセージを毎日お届けします。「生後〇日」と表示されるのでアプリをダウンロードしてチェックしてみてくださいね。
▼無料インストールはこちら▼
※この記事は2025年1月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。





