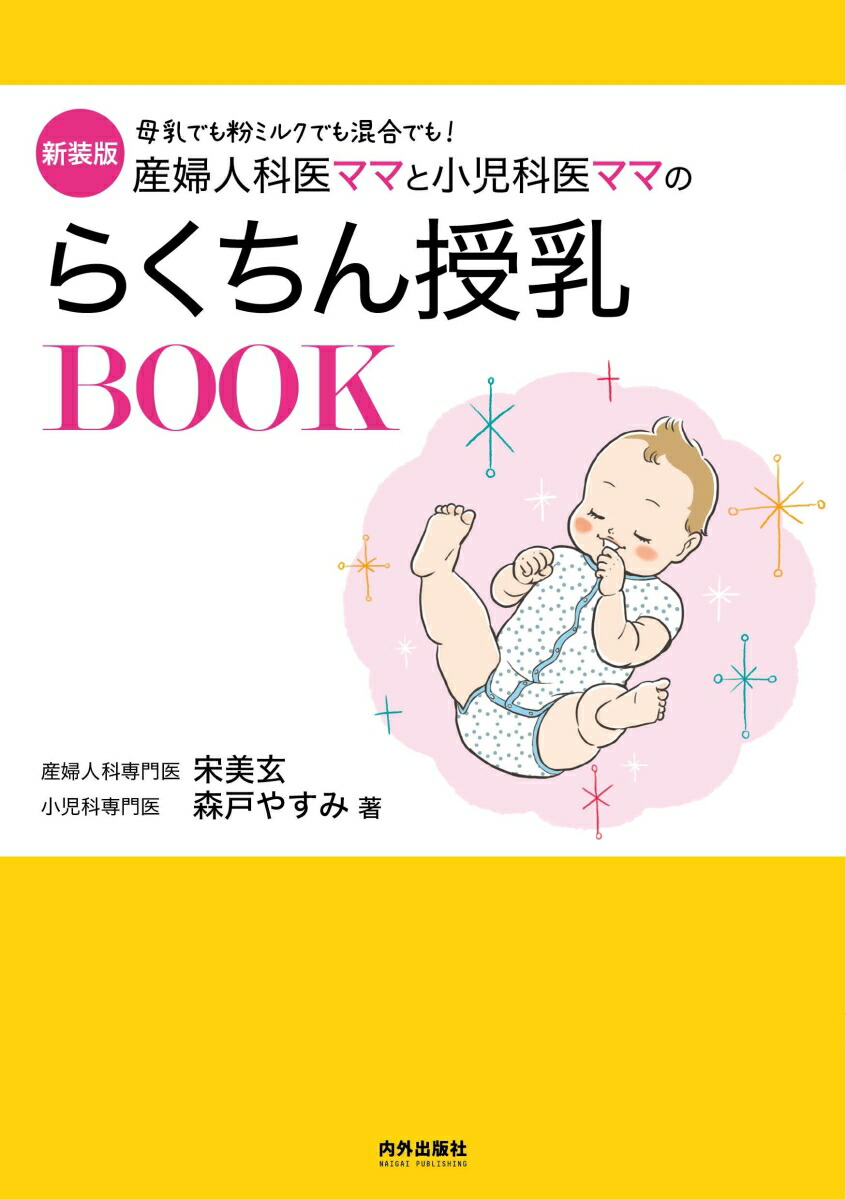【小児科医監修】母乳育児のメリットや食事との関係は?母乳育児の基礎知識
赤ちゃんにママの母乳を与えることは、赤ちゃんにとってもママにとっても良いとされています。ここでは、母乳育児のメリットや、母乳と食事の関係、母乳育児がつらくなったときに考えたいこと、母乳はいつまで与えれば良いのかを解説します。母乳育児について理解することで、赤ちゃんとママにあった授乳スタイルを見つけられると良いですね。
本ページはプロモーションが含まれています
この記事の監修

目次
母乳育児とは?
母乳育児とは、文字通り赤ちゃんへ母乳を与えて育てることです。母乳育児を含め、赤ちゃんへの授乳方法は3つあります。母乳だけを与える「完母」(完全母乳栄養)、粉ミルクだけを与える「完ミ」(完全ミルク栄養)、母乳と粉ミルクを与える「混合」(混合栄養)があげられます。
最近では、授乳の種類にかかわらず、少しでも母乳を与えることが推奨されています。授乳に慣れるまでは試行錯誤が必要ですが、ママにも赤ちゃんにも、母乳で育児するメリットがたくさんあるためです。
ただし、過度に母乳にこだわる必要はありません。大切なのは、ママと赤ちゃんが心も身体も元気に、リラックスして過ごせることです。母乳育児について理解することで、ママと赤ちゃんにあった授乳スタイルを探すことができると良いでしょう。
母乳育児のメリット

赤ちゃんに必要な栄養が十分に含まれている
母乳は赤ちゃんにとっての完全栄養食品とも呼ばれ、およそ生後5~6ヶ月までに必要な栄養素がすべて入っています。三大栄養素といわれるたんぱく質や、脂質、炭水化物のほか、微量栄養素のビタミン、ミネラル、そしてホルモン、酵素などの成分がバランス良く含まれているのです。
赤ちゃんの成長にあわせて栄養バランスが変化していくことも母乳で育児するメリットといえるでしょう。たとえば、産後すぐの初乳は脂質や糖質が少ない分、免疫物質が特に多く含まれています。また、個人差はありますが、産後一週間ごろからは脂肪と糖質が増加し、赤ちゃんの成長に必要な栄養がまかなえるようになります。
赤ちゃんを感染症や病気から守る
母乳には、赤ちゃんを感染症などから守る免疫物質が豊富に含まれています。そのため、小児糖尿病や、小児がん、中耳炎になるリスクが低いといわれています。SIDS(乳幼児突然死症候群)との因果関係ははっきりしていませんが、母乳育児をした赤ちゃんは発症のリスクが減少するという考えもあるようです。
赤ちゃんの発達を促す
赤ちゃんがママのおっぱいを吸うとき、自分の舌や顎を使って母乳を飲みますね。その際に、吸う力が強化され、舌や顎、顔の筋肉が発達します。
赤ちゃんに安心感を与え、ママはリラックスができる
母乳を与えるときは、ママが赤ちゃんを抱っこして密着しています。このとき、赤ちゃんはママの温かさを感じ、安心感を得ることができます。
また、赤ちゃんが母乳を吸う刺激により、ママが子どもを守ろうという気持ちが作られるといわれています。これは、母性ホルモンとも呼ばれるプロラクチンの分泌によるものです。
プロラクチンには、授乳中のママをリラックスさせ、眠気を誘うはたらきもあります。授乳期間中は、夜に何度も赤ちゃんに起こされますが、プロラクチンのおかげでスムーズに目が覚め、授乳した後にはすぐに眠りにつくことができるのです。
このように、直接母乳を吸わせることは、スキンシップによる安心感、信頼感を生むだけでなく、ママをリラックスさせ、授乳を助けるはたらきもあるようです。
赤ちゃんの変化に気づきやすい
母乳の成分が直接肥満防止につながるかどうかということは未だ解明されていないようです。しかし、母乳の成分と、赤ちゃんが欲しがる母乳の量には関係があるようです。
母乳はその時々にあわせて成分が変わります。赤ちゃんがおっぱいを吸っているうちに母乳は脂肪の量がだんだんと増えて、吸い始めの2~3倍になり、カロリーも高くなります。そして、この母乳の成分の変化が、赤ちゃんの飲む量の調整に役立っていると考えられています。
生まれたばかりの赤ちゃんはまだ満腹感がわかりません。しかし、母乳の成分変化により、飲む量を調整することができるのです。このことから、母乳は飲みすぎによる肥満を抑えられているといわれています。
加えて、おっぱいを吸うという行為は多くのエネルギーを使うため、太りすぎを防ぐといわれています。
ママの産後の身体の回復を促す
授乳の際、赤ちゃんが乳頭をくわえる刺激により、オキシトシンというホルモンが分泌されます。オキシトシンは、産後の子宮の筋肉を収縮させ、子宮の回復を早める役割があります。
また、オキシトシンは「しあわせホルモン」とも呼ばれ、ストレスを緩和する働きもあります。このホルモンは、乳頭からの刺激だけではく、赤ちゃんのことを考えたときなどに多く分泌されると考えられています。
しかしオキシトシンは、ママがストレスを感じたたきや、緊張したときに分泌されにくくなってしまいます。よって、産後の身体を回復させる上で、ストレスを緩和させることも大切といえるでしょう。
ママが乳がんや卵巣がんにかかりにくくなる
日本乳癌学会によると、エストロゲンの分泌が、乳がんの発生に関与しているとされています。よって授乳期間中はエストロゲンの分泌が低下するため、乳がんのリスクが下がるとされています。授乳期間が長いと、乳がんにかからないわけではありませんが、乳がんにかかるリスクを下げるともいわれています。
また、卵巣がんになるリスクも下がるとされているようです。これは、授乳中に月経がない期間があることで、排卵の回数が減ることに起因すると考えられています。
赤ちゃんの知能や精神的、感情的、社会的発達が良くなる?
2000年以降、母乳と知能の関係に関する研究結果がいくつか発表されるなど、母乳育児を奨励する話題が多く取り上げられています。しかし、知能や精神的、感情的、社会的発達と母乳の因果関係については諸説あるようです。
たとえば、1999年から2010年、ボストン小児病院の研究チームでは、1312人の子どもとその母親を対象に、母乳育児をした際の子どものIQを検査したようです。結論として、「母乳を与える期間が長いほど、子どもがより賢くなる」としています 。
これに対し、「母乳育児を知力は多元的であり、1つのこと(母乳育児だけ)が 直接大きな差をもたらし得るという考え方には賛同できない」という意見もあるようです。母乳を与えるということ以外の外的要因をある程度は排除して出した結論であるものの、完全には排除しきれていないだろうという見方です。
手軽に授乳できる
母乳を直接授乳させる場合、常に赤ちゃんにとって適温で清潔な状態が保たれています。ミルクを冷ましたり、哺乳瓶を洗って消毒したりという工程を省けるのも母乳で育児するメリットです。
また、赤ちゃんが欲しがるときに与えられることや、夜間寝たままあげられる、道具を揃えなくて良い、出かけるときの荷物にならない、ゴミが出ない、ミルクを買っていないと慌てることがないなど、手軽に授乳できるという良さがあります。
ミルク代がかからず経済的
ママのおっぱいから授乳ができるため、母乳で与えた分は、ミルクを購入する費用がかからない点で、経済的といえるでしょう。
母乳育児のデメリット

1. ミルクに比べて、飲んでいる量がわかりづらい
2.授乳間隔が短くママが疲れてしまうこともある
3. 母乳分泌が悪いと赤ちゃんの体重が増えにくい
4. 赤ちゃんがミルクに慣れていないと、他人に長時間預けられない
5. 乳房、乳頭のトラブルが起こることがある
6. 生後5~6ヶ月を過ぎると、鉄・ビタミンDが不足しがち
母乳での育児はメリットもたくさんありますが、デメリットもあります。デメリットがあるために母乳とミルクを天秤にかけるということではなく、それぞれの特徴を理解したうえで、母乳とミルクをうまく組みあわせていけると良いですね。
母乳育児と食事の関係

母乳の質・量と食事の関係については近年さまざまな研究が進められています。これらの研究から、母乳の質や量は、ママの食事の影響を受けないということがわかってきています。
以前はママの食事が母乳に影響すると考えられていたため、脂肪分の多いもの、塩分の多いものはできるだけ避けるようにと指導がされていました。しかし、現在では脂っぽい食べ物が原因で乳管が詰まるというエビデンスはなく、特定の食品を制限しても赤ちゃんのアレルギーの予防には効果がないという考えが主流です。
ただし、必ずしも食事に気を遣わなくても良いということではありません。授乳中は1日に2,300kcaL±300kcaLほどのエネルギーが必要とされています。バランスの良い食事で、授乳に必要なエネルギーを摂取し、血流を良くすることを心がけましょう。
母乳育児がつらいと感じるときは?

母乳育児にはメリットがたくさんある一方で、母乳育児がうまくいかないときにはつらく感じることも多いでしょう。必ず母乳でないといけないというわけではなく、ミルクにも栄養はたくさん入っています。また、完全ミルク育児でも赤ちゃんは元気に育っています。
最近では、さまざまな場所で母乳育児を勧める傾向が強いようですが、母乳育児にこだわりすぎて、うまくいかないときにママが思い詰めてしまうような必要はありません。
初めての赤ちゃんの場合はもちろん、二人目の赤ちゃんであっても、個人差や環境の変化などで悩んでしまうことがあるかもしれません。ママだけで思い悩まないように、家族や身近な人、助産師や母乳外来などへ相談すると良いですよ。
また、母乳育児がつらいと感じるときには、ミルクを上手に取り入れると良いでしょう。ミルクと混合にすると、パパもミルク作りや、授乳を手伝うことができるなどのメリットがあります。何よりもママと赤ちゃんがリラックスすることを大切にしながら、授乳や育児と付きあっていけると良いですね。
母乳育児はいつまでするの?

離乳の開始は生後5~6ヶ月ごろから
厚生労働省の見解では、離乳の開始は生後5~6ヶ月ごろ、離乳を完了させる時期は生後12~18ヶ月ごろが目安とされています。また、ユニセフやWHOでは、短くとも2歳までは母乳育児を続け、生後6ヶ月の初めには母乳に加えて適切な補完食(離乳食)を開始することが推奨されています。
離乳とは、母乳やミルクだけでは不足する栄養やエネルギーを補完するために、幼児食に移行する過程を指す言葉です。離乳期は、授乳のリズムにそって赤ちゃんが欲しがるときに欲しがるだけ母乳をあげてよいとされています。赤ちゃんのペースにあわせて離乳を進めていきましょう。
卒乳・断乳の時期は状況にあわせて決める
母乳育児をやめることを卒乳もしくは断乳といいます。卒乳とは赤ちゃんのタイミングで母乳育児をやめることを指し、断乳とは家庭の状況などにあわせて大人が主体となって計画的に母乳育児をやめることをいいます。
ママの母乳の出方や、赤ちゃんがうまく母乳を飲めるかは個人差があります。母乳があまり出ない場合や、授乳による睡眠不足が続いてつらいという場合、早く授乳をやめたいというママもいるでしょう。
また、ママと赤ちゃんの調子だけでなく、家庭環境にも授乳スタイルをあわせなくてはなりません。産後、できるだけ早くに仕事復帰しようと考えているママの場合、日中に授乳をすることは難しくなるため、断乳を考えたり、赤ちゃんにミルクや、哺乳瓶に慣れさせたりする必要があります。
ママの母乳の出や、赤ちゃんの飲み方が安定してから、今後どういうスタイルで授乳をしていくのか家族へ伝え、理解してもらうことをおすすめします。このとき、断乳や卒乳についても考えましょう。周囲へ理解してもらうことで、手伝ってもらえることが増えると良いですね。
母乳育児についてのおすすめの本
授乳について迷ったとき、ちょっとした疑問を解決したいときに、頼りになる本があると安心できるかもしれません。以下に紹介する本は、文献をもとに中立な立場で書かれた授乳本です。参考にしてみてください。
近年では、母乳育児が盛んに推奨されていますしかし、母乳がうまく出るママだけというわけではない現状もあります。この本は、そんなママにも読んでもらいたい本です。
本書では、授乳全般についての疑問や悩みに対して、産婦人科医と小児科医である著者2名が、中立な立場から根拠を示しながらわかりやすく解説されています。
家族と母乳育児について話そう
母乳育児は赤ちゃんだけでなく、ママにも良いことがたくさんあることがわかりましたね。できるだけ母乳で育てたいというママも多いでしょう。しかし、母乳にこだわり過ぎず、ミルクも上手く取り入れながら、ママと赤ちゃんに合ったスタイルを探せると良いですね。
また、母乳育児において、家族のサポートも大切になってきます。家族にも授乳について伝えることで、どうやってサポートすれば良いかわかりやすくなるでしょう。今困っていることや、今後どのように断乳・卒乳するのかなど、家庭の環境の変化にもあわせて話し合えると良いですね。
※この記事は2025年2月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。